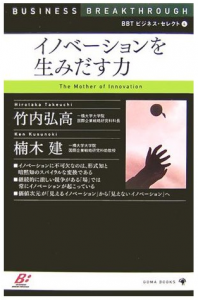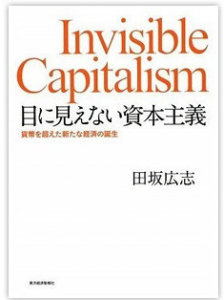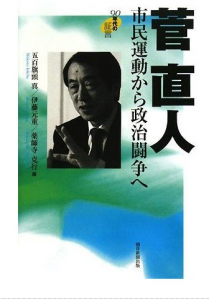著者に経済分野を書かせたら右に出るものはいない。本田宗一郎と幾日も共に過ごし、取材をした著書があるのは知らなかった。本書は引退後の本田宗一郎の取材を元に書かれた一冊である。
現役の本田宗一郎の著作は数多い。また私の履歴書など本田宗一郎自身が書かれたものもある。しかし引退後について数少ないように思う。戦後設立された日本企業で最も成長した1社にあげられるのがHONDAである。最近ではジェット機の製造も開始された。このように未だ成長がやまないHONDAである。良く言われることだが、その要因を組織文化につきると思う。HONDA・DNAということになるのだろう。
サスティナブルなHONDAの理由
特別な入社試験を課しているという話は聞いたことがない。また社内育成に特徴はあると思うが大きく取上げられることもない。経営環境やマーケットが変化をすれば組織文化も変化をしなければならない。こうしたことが発展的変化を可能とする理由は何か。そのヒントが見つかった。
「企業といっても、人間が主体です。人間を抜いたら、何もない。人間がその気にならなけりゃ、何もはじまらない。それには平等感というか、一人一人が大事にされているという認識がないと….その点では、世界中でうちぐらい人間を考えている企業はない、と思います」
つきなみではある。しかし結局こうしたことが発展の礎なのだと思う。“人が企業を創る”のである。就職不況の関係から院に行く者も多いが概ね22歳で就職をする。就職先の違いは数年で考え方を変える。もう数年経つと能力に違いが見られる。30代も半ばになれば先が見え始める。ようするに仕事に“わくわく感”が無くなるのである。しかしHONDAなら“わくわくする日々”をおくれそうである。相思相愛な関係と言い換えることができる。
夢を見られる企業を創ることが経営者のひとつの使命なのだと本書を通じて感じた。厳しい局面だからこそ“わくわく感”を忘れてはならない。まず自ら実行することがスタートだと思う。
日本の平均寿命は82.3歳(2005)である。世界的に見ても長寿国であることは間違いない。ちなみにロシア人男性は60歳を下回る(2005)。ロシアには年金問題が発生しそうにないかわりに“遅咲き偉人”も見つかりそうにない。
著者はライフワークとして「人物記念館の旅」を続けているとのことである。本書はそこで出会った偉人について論じた一冊となる。“人の偉大さは人に与える影響力の総量で決まる”と結びつけている。経営者で言えば“京セラ稲森名誉会長”などがあげられるのかも知れない。
本書はここで19人の偉人について紹介をしている。その切り口は“遅咲き”である。遅咲き偉人に対する著者の見方を引用して紹介したい。
「遅咲きの人には長く仕事をしている人が多い。世に出るまでの修行の時間が長く、その間にじっくりと自身の力で成熟しているから、遅咲きの人は長持ちしている。したがって影響力の総量において、実は早咲きの人に比べると圧倒的に勝っているということになる。そして彼が生きた時代を超えて、今日に至るまでその影響が及ぶということになると、その総量はとてつもなく大きくなり、偉人と呼ばれるようになっていく」
当然のことながら遅いから良いのではない。修行を積上げ、熟成する期間を保つことが重要なのである。経営者には“強さ”が必要である。胆力とも言える。いつのまにか自分を含め“胆力”のある人が少なってきたように感じる。これは経営者だけではない。政治家にも共通したことではなだろうか。すさまじい戦中戦後を経験した政治家はなにか代えがたいものを感じた。しかしいまそれを感じることはまずない。これは生きることが修行であったと言えるからなのかもしれない。
“命がけの修行と成功経験”これが偉人となるキワードのようにも感じる。本書から19人偉人の生き方を学んだ。これからの人生の参考としたい。機会を見て一人ずつ紹介したい。
変革型ミドルのための経営実学―「インテグレーションマネジメント」のすすめ
“変革型ミドル”の定義を明らかにしなければ本書レビューは困難である。著者の言葉を引用すると「経営が分かって実務を行うミドル、経営が分かっているからこそ組織変革の道筋が見え、トップとの積極的なコミュニケーションを図るミドル、経営目標の共有だけではなく、その立案にも自主的に参加しようとする組織人」とある。本書は大企業組織だけでなく中小企業でも大いに参考になるのではないかと考える。むしろ中小企業のほうが複雑な組織でない分効果を得やすいのではないかと思う。
中小企業経営の文脈に置換すると、こうした視点を持った“右腕人材”がいる企業は成長が早い。こうしたことは数多くの論文からも明らかとなっている。ここでは中小企業の文脈に置換してレニューを進めたい。本書は“鳥の目と虫の目~”と説明がなされている。要するに俯瞰して全体を見る視点と現場からの目線ということになる。どこか当たり前のような気もするが実際これができる組織人は少ない。これを5代閉塞要素として本書ではまとめている。
① 階層思考 指示事項は疑わず要素分解する思考癖
② 取り敢えず思考 一手先しか読まない思考癖(考え方の癖)
③ 権威主義 自分自身では考えない思考癖
④ 処罰志向責任感 責任とは処罰か辞任という思い込み
⑤ 嫉妬容認風土 結果が良かった人の足は当然引っ張るという常識
とある。組織によってはこうしたことが組織文化として根付いている企業もあるのではないだろうか。特に階層志向や嫉妬容認は良く目にする。そもそも階層が高い事が問題なのだが、経営者が自らを高めるために高くすることは多い。こうしたピラミッドは求める組織人材は権威志向が強く他組織で通用しないだろうなと思うことが多い。こうした組織で見られるは“経営者の指示を考察せず実行する”ことが多い。当然経営者の失敗もある。これでは右腕人材になれるはずはない。
嫉妬容認風土はいうまでもない。嫉妬者が自己の存在意義を問うようなケースもある。こうなるとネガティブサイクルが回りだし全体に悪い影響を与え始める。賞罰は誰もが納得が得られるようにすることが大切である。
このように数多くの視点で企業経営を見直させてくれるのが本書である。大手企業のミドルが対象かと思う。しかし自己の文脈に落とすことで多様な発想が生まれる一冊である。
VIRAL LOOP というとインフルエンザが流行るようなイメージがある。もちろん本書で述べられるのは VIRAL Marketing に関してある。まず本書でのバイラル・ループ定義について明らかにしたい。「バイラル・ループというのは、インターネット状でブログやツイッター、ユーチューブなどのメディアを経由して、情報がウィルスのように伝播していく現象のことだ」本書はこうしたバイラル・ループのケースを取り上げた一冊なのである。
VIRAL LOOPはハズ・マーケティングのデジタル化と解釈している。最近は“選挙”にも影響を及ぼしている。本書事例紹介のオバマ大統領の政治献金などすさまじさを感じる。しかしハズ・マーケティング=口コミマーケティングは別段新しい手法でもの何でもない。旧来手法のひとつとしてタッパウエアーの解説を紹介したい。
「…彼は非常に口がうまい人物だった。化粧品の訪問販売で知られるエイボン社などで、バイラル戦略を40年近くにわたって実践してきた経験を持ち顧客啓発が必要な商品は、ダイレクト販売に限ると信じていた。もしジーンズを売るなら、ダイレクト販売の必要はあまりない。ジーンズとはどんな製品でどんな用途なのか、誰でも知っている。しかし目新しい商品(たとえば、食べてみないとおいしさがわからない商品)を扱うとなったら、ダイレクト販売が最もふさわしい戦略だろう。ゴーイングスは、友人(friend) 隣人(neighbors)親戚(relatives)を“FNR”と名づけて重視したFNRはさらに別のFNRを呼び寄せてくれる。「知り合いのお勧めの一品」となればおのずと商品の信頼度が上がる。FNRは、れっきとしたマーケティング戦略なのだ」
SNSはゆるやかなFNRである。“はてな”やカカクコムなどの批評もこの部類に入るのだろう。アマゾンのレコメンデーションもその広い意味で含まれるのかも知れない。店員と対話の上で購入するリアルショプは“店の利益”が付いて回る。しかしバイラルはそうした目的を持っていない。百貨店売上高は10年下落の一途である。こうしたことが遠因とも考えられる。
ツイッターの加入者は震災の影響から増加スピードが高まっている。フェィスブックも同様だろう。ここまで着目されるのは“情報の量と質”に深い関係問題があると感じている。またフェィスブックの“いいね”を始めとした人から承認されることの喜びとも関係性が深いように思う。
バイラル・マーケティングが新しい展開を迎えていることは間違いない。
BBT ビジネス・セレクト4 イノベーションを生みだす力 (BBTビジネス・セレクト)
本書は ① 知識資産 ② イノベーションのパラダイム ③ ポーター賞の3部で構成されている。新書180ページという紙幅から奥深い知を得ることは難しいが知識経営とイノベーションの入口が論じられている。
イノベーションを起こすことが難しいのは明らかである。仮に新たなビジネスモデルを構築できても持続的に寡占化することも困難である。小さな変革を持続的に続けることが企業発展と存続の要素ではないかと考える。本書はこうした考え方を支える知識が詰まっていると思う。
脱コモディティ化
昨今の事業展開はとかくコモディティ化しやすい。これは製造業に限らない。飲食を含めたサービス業や流通なども含む。常に価格競争にさらされていると考える必要がある。コモディティ化の問題解決に経験やコトを売るということが言われている。本書ではスターバックスを例に上げて解説している。
「1カップの値段をコーヒー豆で見ていくと1~2円である。それをパッケージングすると5 円~25円になる。さらにサービスして売ると100 円~200円である。それをスターバックスのように「コーヒー体験」にして売るとどうなるか。250 円から500になるのだ」
経営者に求められるのは、こうした「文脈」を如何に創るかにあると私は考える。顧客に価値を認めてもらうコンセプトを生み出すことが必要なのである。”Willingness To Pay支払意欲を起こさせる事業展開が求められる。こうしたことでもコモディティ化の発生は拒めない。そこで重要なのが“スモールイノベーション”ではないか。
それは日々現場から上がる情報を組織の文脈で解釈し変化をこすことを指す。小規模企業だから可能な経営スタイルである。こうすることでコモディティ化からの脱却が可能になるのではないかと考える。
中小企業経営の実践は経営戦略、マーケティング、組織など各理論を分離して考察すべきでないと考えている。これらのバランスを取りながら企業成長を考えなければならない。当然のことながら資金というリソースもこの背景にある。しかしこうした理論のもとで実践プランを構築しなければそれこそ穴のあいたバケツのごとく資金が漏れていくのである。
コア・コンピタンス
ビジネスプランが重要であることは言うまでもない。しかし概ねのビジネスプランは類推しているのが現実である。また後発企業が真似ることも十分に可能である。そこで重要となるのがコア・コンピタンスである。G・ハメルとC・K・プラハッドは「顧客に対して他社には真似のできない自社ならではの価値を提供する、企業の中核的な力」であると述べている。いわゆる企業内部に培った能力を競争のための資源であるとする考え方であり、リソース・ベースと・ビュー(資源に基づく戦略の見方)と呼ばれるものだ。
他社が真似できるのは“カタチ”だけである。ソフトを真似ることはできない。これは経営者や社員が持つ“暗黙知”である。SECIモデル言う共同化が自社の強みになるのである。ということは経営者や中核社員がKFSとなる。企業のコア・コンピタンスは“ヒト”だということである。要するに“知識”がコア・コンピタンスなのである。2005年に亡くなったピーター・ドラッカーは40年以上前に「知識は新たな世界経済を形成する主な資源で、この生産性が経済活動の要になるだろう。また知識は最も大事な生産資源である」という言葉を残している。
知識資産=コア・コンピタンスの形成が事業成長のKFSなのである。
スモールビジネス・マーケティング―小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム
小規模企業のマーケティングにはお勧めの一冊だ。コトラーを始めとしたマーケティン
グの学術書は数多い。それを元にしたビジネス書は所狭と書店に並んでいる。それはアルファベットを3つ程並べた米国発のマーケティングが軸になっていることが多い。
アメリカ人と日本人は価値観の違う消費者
以前マーケティングが専門の教授に「翻訳本は米国の考え方であって、そのまま価値観の違う日本人に取入るは如何なものか」という質問をしたことがある。確かブランディングの件だったように思う。研究価値があるからと論文を進められた覚えがある。こうしたことはマーケティングに限らない。戦略論、組織論も同様である。企業規模や時代環境によっても大きく違う。一例を上げれば来年の東北地方のマーケティングは大きく変わるだろう。こうしことから“自社の文脈”また“自社のリソース”に如何に落とすかが重要なのである。付け加えれば環境も忘れてはならない。
本書の特徴
本書は博士課程後期の教授に謝辞が述べられている。こうしたことから論文を一般読者ように書きなおしたものだと思う。よってリサーチなどの裏付けがしっかりと取られている。リサーチ結果はグラフや図解で示されている。実際この手の参考文献はいまでも探しているのだが中々見つからない。
内容は小規模企業の強みを仮説としてその検証を行っている。小売店を中心とした仮説検証であるが“企業の文脈”に置換することは十分可能である。
小規模企業でマーケティングに携わる方には価値ある一冊だと思う。
本書副題は【貨幣を超えた新たな経済の誕生】とある。当然のことながら貨幣経済が無くなるわけではない。一言で言えば“尺度の多様化”である。プータンの幸福度も一つの考え方である。著者はよりロジカルに多様化について論じる。著者の本の特徴は単なる“行間を読む”ということを超える。背景、コンテクスト、周辺知識を併せて考察しなければならない。考えるに2度目はまた違ったコトが見えるように思う。
“21世紀の経済は弁証法で予見できる”と著者は述べている。弁証法とは色々な定義があるがごく簡単に言うと次のようになる。
弁証法とは、いろいろな解釈がありますが、基本的には議論においての解釈に使われていると考えます。【一つの定義、意見,,,,テーゼ】に対して反対の意見【反対定義…アンチテーゼ】がある。相互の意見、対話から新たな見識(高次元)が生まれる。【1つの結論…シンテーゼ】。この時うまれた高次元の見識に達するシンテーゼを【アウフヘーベン】という。
要するに、議論を行って、より高い次元の結論を出す方法論である。
アダムスミスからのパラダイム転換
“弁証法により見えない経済を見る”または“弁証法ならば見える”ということが本書の背景にある。またこうしことを重視しなければならないと論じている。ここで著者の貨幣経済についての考え方を紹介したい。
「アダスミスが語った“神の見えざる手”という言葉。それは市場において、自由競争に任せていれば、自然に神の見えざる手によって、市場に均衡と秩序が生まれるという思想である。しかし市場という複雑系のおいては、そうした自己組織化と創発が起こる可能性がある半面、条件によっては市場システム全体が崩壊してしまう可能性がある。そのことを複雑係が教えているのである。すなわち神の見えざる手は、市場を必ずしも均衡と秩序に導くだけではない。それは、ときに市場をカダストロフィー(破局)に導き、経済システムを崩壊させる可能性があることを教えている。」と述べている。複雑系経済とは“生命的な性質を強めた経済システム”のことに他ならない。
我々は生態系の変化するような経済環境におかれているとも言えるのだ。バタフライ効果を例題に本書では論じていく。見えない環境下で重要視されるのが“共感”のパラダイムである。
少し紙幅が足りないようだ。次回続編を書きたいと思う。
本書初版は2005年。著者は伊藤忠商事会長時に執筆された本だ。著者は現在中国大使として北京におられる。こればかりは外務省と柵のない民主党政権ならではの起用だったと思う。著者はプロパー社員としてCEOまで上り詰めた人物である。一般に創業者は大手企業サラリーマンを終え起業する人物は少ない(日本政策金融公庫資料等による)。生き方が違うのだと感じている。しかし“経営”ということについては参考になる部分は多い。
大手企業の経営と中小企業とは確かに違うのだと思う。人、モノ、カネ、情報。そのすべてにおいてスケールも質も違う。組織で考察すると人数が少ないためにすべてが見える。従業員は経営者の行動、考え方、生活すべて自己の文脈で一致しているか否かを判断している。あまりにも乖離していれば離職へと結び付く。大手企業であればたとえ上司であってもそうしたことは少ない。スイッチングコストや転勤などがあることもひとつの要因である。そうしたなか実際の経営は執行役員制度が普遍化しつつある。CEOは全体を俯瞰して考察する。これについては中小企業の経営者も同様である。細部ばかりを追いかけること無く俯瞰して考察しなければならない。
経営に対する考え方 論理
著者の経営に対する考え方を取り上げて見たい。
「経営というのはまず論理がある。したがって我々のキャッチフレーズは論理に裏打ちされたものでないといけない。論理的に説明をするとなると、今度は学者みたいに非常に難しい言葉になりますから、そこをわかりやすく表現することが大事になってくるわけです」
中小企業経営者で“論理の重要性”を取り上げる人あまり目にしない。しかし経営品質協会の受賞者の考え方を見ているとその重要性を強く感じる。またユニクロや星野リゾートなど急激に成長している企業は論理に重点を置いている。ユニクロは一橋大学大学院と連携している。また星野リゾートは“星野リゾートの教科書”なでも明らかになっている。
2社ともに中小企業からの成長である。こうしたことから明らかなようにサスティナブルな成長を目指すには“論理”が重要なのである。ロジカルな弁証法で軸を立たせることが成長を固める要素であると考える。
経営に対する考え方 姿勢・生き方
ここでは著者の倫理や理念は明らかとなってはいない。しかしその一面を次の一節は教示していると思う。
「…人間の心は弱いものです。「神も仏もないのか」と思うほどの黒を味わったとき、さらに努力を重ねるのは並大抵のことではありません。そんなとき宗教を信じるかどうかは別として、誰かがかならず見ているんだと思って努力を続けたほうが、自分の心を納得させやすいのは事実でしょう。生きていく上で、そう考えたほうが説明のつくこともあります。私の解釈を言えば、神とは自分以外のすべてです。すべての人が自分を見ている。そう信じて一生懸命やっていくことで、人間は強くなっていくものだと思います」
これが著者の生き方と捉えられる。とにかく“一生懸命やっていく、やり抜く”やはりこれが重要なのだ。京セラ名誉会長の稲森氏が“誰にも負けない努力”という事を言われる。これは相通じるものだ。これを可能にする“人”に感動を覚える。その結果が著者の中国大使や稲盛会長のJAL会長は“国家へのご奉公”なのだと思う。ここでは国家のために努力をしているのだと感じる。愚直に一生懸命やっていくこと。それが必要とされる人になる最初の一歩なのだろう。
本書は1990年代を振り返り当時のキーパーソンとの対談をまとめた一冊だ。本書が興味深く読めたので他4名についても購入した。追って紹介したいと思う。
まず90年代がどういう時代であったかを振り返りたい。最近のでき事から振り返れば神戸の震災がまず浮かぶ。まもなくオウム真理教事件が発生する。バブル崩壊後の厳しい時代であった。本書では次のように紹介している。
「すでに冷戦時代は終わりを告げていました。そして、いよいよ平和が訪れるかと思いきや、湾岸戦争が起き、「テロ」や「北朝鮮の核」という新たな脅威に直面しました。一方国内政治は「混迷」の時代だったと言えるでしょう。自民党による単独政権時代が終わり、軸足のはっきりしない権力闘争が繰り返されました。国内経済はさらに惨憺たる状況でしたバブル経済の崩壊とそれに続く不良債権処理問題と金融機関のあいつぐ破綻国家財政も巨大な借金に悲鳴をあげました。まさに長期不況に沈み込んだ10年でした」
暗い印象を感じる。しかしこうした中からITブームが生まれる。いついかなる時も前向きなこともり二律背反か。当時の印象を言えばITや携帯電話の自由化などもあり“産むための苦しみ”という印象があった。本書で取り上げる現首相の“菅直人”はこうした激動の中で成長著しい政治家であったと感じる。社民連、さきがけ、民主党と政党を移りながらそのつど大きく変化をする。実際、社民連の記憶あまりない。やはり“さきがけ”での厚生大臣だろう。薬害エイズ問題、カイワレとメディアで取上げられた。これが今の地位のきっかけではないだろうか。
本書を紐解くにあたってひとつの問題意識があった。リーダーシップの不足、献金問題などから総理としての基盤は相当ぐらついている。首相の考え方を知ることでこれからの対応を推測するということである。
今後の菅政権を推測
問題意識を刺激する一節を紹介したい。村山総理(自社さ政権)辞任についてだ。
菅「95年1月に阪神・淡路大震災があって、村山総理が辞めたのはその翌年の1月ですね。ある意味では村山さんは燃え尽きちゃったんですよ。疲れちゃったんです。これは若干あと知恵ですが、村山さんが自民党に政権を譲ったのは大間違いだったと思うんです。本来なら村山さんは、次の展望を持って自分の手で衆院を解散すべきだったんです。村山さんは北海道知事だった横路孝弘さんあたりを後継にして、どこかの時点で解散して、今度は自民党に頼るかどうかはべつとして「自分たちが主導の政権をつくるんだ」と打ってでなければいけなかったんですよ」
この文脈から読み取れるのは【解散】【後継】である。当然のことながら【主導】的にとなる。これに本書全般の文脈を重ねると、どうすれば【自らが主導】になれるかが軸でありどういう【国造り】をするかは感じられない。リベラルなど言葉はでるが極めて具体性に欠ける。これだけの文字数なので相当のインタビュー時間を要しており割愛されたとは考えづらい。こうしたことから考えると次の仮説が生まれる。
【主権は国民のためでなく、民主党またはみずらかのグループが軸となる政治をどう創出するか】が軸となる。ということである。スケールは違うが村山政権も震災後でありその時の考え方を論じている。あたりまえのようだがやはりここに尽きるのだ。
“国民の為”ということを本書からは感じることは出来なかった。また今の政権からも感じることはできない。それは他の政党も同様である。政治とはそういうものなのか。他国と比較するにはあまりにも判断材料が少ない。しかしどうも“日本”の政治には違和感を覚える。こうしたことを踏まえ経営判断をしなければならないことだけは間違いない。