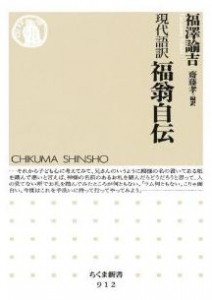訳者、明治大学教授・齋藤孝氏は最近メディアへの登場も多く、ご存知の方も多いかと思う。このブログでも著書や推薦図書を何冊か取り上げている。“学問のすすめ”もそうであったが150年をゆうに超える古い本を訳者は実におもしろく、リアリティを持って読ませる。原典の素晴らしさは当然のことであるが、これが訳者の実力なのかと感じさせる。
さてここで本編についてのレビューをしてみたい。
福沢諭吉は慶応義塾大学の創設者であり、日本有数の啓蒙思想家である。国の礎を築いた一人である。その人物がどのような『人間』であるかの端緒を本書から伺い知ることができる。「酒と福澤」は心の内を良く知ることができる。福沢諭吉は自らが政治家や官僚ではなく、教育・思想家の道を歩んだ。江戸幕府での実績を捨て、こわれるも自らの道を歩んだ。昨年の流行語に『断捨離』という言葉がある。本書を読みながら『断捨離』が的を射た人物ではないかと感じた。
「人の知恵を借りようとも思わず、人の指図を受けようとも思わず、人間万事が運命だと覚悟して、務めることはあくまで根気よく努めて、種々様々のやりかたを工夫し、交際を広くして好き嫌いの念を断ち、人に勧めたり人の同意を求めるなどということは、人並みにやりながら、それでも思うようにならないときは、なおそれ以上に進んで哀願しない。ただ元に立ち戻ってひとり静かに思いとどまるだけです。つまるところ、他人に頼らなないというのが私の本願で、この根本方針は私がいつ思い立ったのやら、自分にもこれという覚えはないが、少年の時からそんな心がけ、いや心がけというよりもそんな癖があったように思われます」
知を得るためには最善の努力を積む。しかし何やら淡々としているイメージを受ける。訳者はそのあたりを次のように解説する。
「福澤は自身の精神を「カラリ」としたと表現していますがまさにその形容がぴったりです。…福澤の知性には、スタイルがあります。単なる合理性というのではありません。自分自身の気質を良く知っていて、それに合わせた自分の型を持っている。だから相手や状況に振り回されずにすむ」
自らの『型』を知る。『型』造ることは理念にも繋がるのだと思う。ふらつかない、人に惑わされない。これだけでも人は進歩しやすくなる。福澤という人物も淡々と日々の積重ねがあったに過ぎないと思う。明日の夢を語る時はすでに進んでいることが大切だと思う。ときとして語ることが現実を回避していることがある。